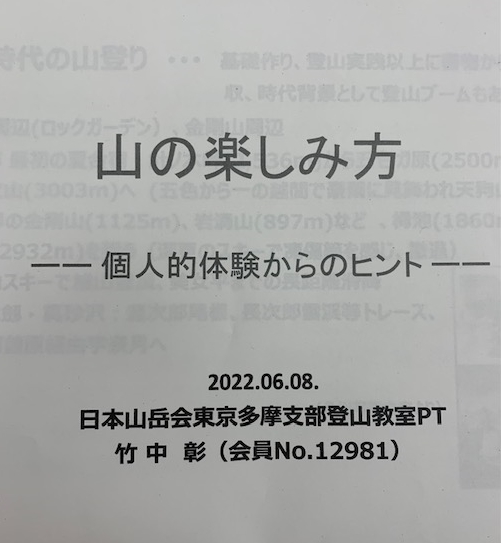日時
2022年6月11日(土)-12日(日)
天候
11日曇り 夕方から雨
12日正午まで雨のち曇り 気温15度
参加者
10名 L鬼村、SL富永、中原、斉藤、畑中、佐久間、植草、人見、土田、川合
行程
1日目 会津高原尾瀬口 14時集合―タクシー―15:30 湯の花温泉 民宿 山楽 泊
2日目 山楽発 6:30-タクシー-7:10猿倉登山口7:25―9:20田代山山頂9:30-
9:35田代山避難小屋9:50-11:35帝釈山11:50―13:26田代山避難小屋13:40—
14:25小田代―15:35猿倉登山口―17:00 夢の湯温泉 解散
記録
梅雨の真只中、入山前泊の夜半は強い雨であったが、当日(6/12)の早朝は小降りとなり宿泊した民宿「山楽(さんらく)」をクルマ2台に分乗して猿倉登山口に向かった。
丁度この日は田代山の山開きの日で、南会津町のご担当者と思われる皆さんが登山口で出迎えてくれ、登頂記念の素敵な記念品を頂いた。その後、準備体操と打合せ(雷遭遇の際の対処法、等)を行い、7:25に登山開始。田代山は富士山のような形をしており、天辺の湿原に至るまでは登山口からいきなり急登が続いた。雪解けとこの日の雨により山道が非常にぬかるんでいたため、朝一の登りとしてはきつかった。
9時過ぎ、登り切ったところにある弘法池という池塘に到着。好天であればここから、池塘越しに会津駒ヶ岳の雄大な山容が眺められるらしいが、この日は完全にガスっていて何も見えなかったのでそのまま通過。9:20、田代山頂(1926m)の標識に着くも、ここでも展望は皆無であったため、集合写真を撮影して先を急いだ。気温約8°で、遮るものに乏しい湿原を強い風が吹いていたため急に寒気を感じたが、雨のため雨具の下に着込むことがままならずそのまま歩き続けた。雨天歩行中の衣類調整に工夫が必要であることを痛感。
9:35、湿原西端に位置する避難小屋(弘法大師堂)着。頑丈な建物にトイレと休憩場所があり、やっと一息がつけた。20分程度の休憩の後、二つ目のピーク帝釈山をめざし出発。ここからは残雪が現れたものの、木道が露出していたためクランポンは装着せずに歩行を続けた。アップダウンを重ね、帝釈山直下ではロープやハシゴが設置された急登を登り切り、11:35帝釈山山頂(2060m)に無事到着。展望がなかったので、ここでも集合写真撮影と簡単な休憩だけで済ませ、11:50下山の途に着いた。
避難小屋までの帰路はピストンの同じ道ながら、滑りやすい下りの残雪に苦労して、13:26に避難小屋到着。簡単な休憩後、湿原の帰路横断に向かったが、行きとは別の南側木道を選択。ここを通過中に、時折ガスが晴れて湿原の広い範囲と遠くの山並みを望むことができ、メンバーから喜びの声が上がった。行きに通った弘法池を通過した後、朝一で息を切らせて登った急斜面を下り切って、猿倉登山口に15:40に全員無事下山した。
会津高原尾瀬口駅近くの「夢の湯」で入浴した後、同駅で解散、各自家路に着いた。
<その他ハイライト>
・皆が往路で乗ろうとしていた東武特急「リバティ」に自由席や立ち席がなく、予約指定券がなければ乗車できないことが前日に判明。予約未済のメンバー(含、筆者)は、直前に予約をあたふたと入れることや、後発の列車しか結局取れず遅れて合流することを余儀なくされた。集合場所までの移動にも油断せず慎重な準備が必要と痛感。
・民宿「山楽」は、リーズナブルな宿泊料金(8千円/泊)、食事、接客面でメンバーの評価高(HP: http://aizu-sanraku.com/)。近くに共同温泉が4箇所(内2箇所は混浴)あり楽しめる。今回女性陣は混浴を物ともせず、全湯制覇!
・田代山は花で有名。今回は大規模な群生は見られなかったが、珍しい種類の植物(チングルマ、etc.)に出会うことができ、花に詳しいメンバーは写真撮影に余念がなかった。筆者は知識がなく、横で見ているだけであった。
(文:土田圭滋、写真: 鬼村邦治、中原三佐代、土田圭滋)
感想文
コロナ禍にあり、遠出が憚れていましたが、今回思い切って泊まりの山行に参加しました。生憎の雨になりましたが、先輩たちの指導の元、無事に下山出来ました。前泊の温泉巡りと当日の温泉に心から癒されました。
(川合 薫)
動画
写真

田代山山開きの幕前写真

田代山頂集合写真

帝釈山集合写真

田代湿原歩行

田代山登頂記念品